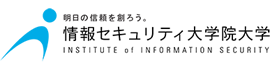シラバス
情報デバイス技術(前期2単位)
教授 松井 俊浩
1.授業のねらい
セキュリティ問題はコンピュータで発生するのであるから、コンピュータを中心とする情報デバイス要素の動作原理、特性、プログラミング、内包する脆弱性を学ぶことは、セキュリティの学修にとって重要である。情報デバイスを構成する要素として、論理素子、コンピュータ、マイクロプロセッサ、メモリ、ネットワーク機器、そしてそれらが一体となった組込デバイスについて論ずる。情報デバイスの開発をARMマイコンとmbed開発環境を用いたハンズオン学習で体験する。
2.到達目標
●コンピュータアーキテクチャの発達の過程を理解し、さまざまなコンピュータアーキテクチャの特徴がわかる
●コンピュータの性能を決める要素や高性能化の手法を理解する
●デバイスが内包するセキュリティ脆弱性を認識する
●IoTに向けて簡単な組込デバイス開発が行える
3.授業計画と開講形態
開講形態は別途通知。
授業に関する情報、また授業で用いるPDF教材は、学生情報サービスのほか、Google Classroom (クラスコード= j5s2dcr) において提供する。Google Classroomは、出席簿や小テストにも使用する。
- 組み合わせ論理回路 加算器、算術論理演算器
- 順序回路 フリップフロップ、スイッチング素子、LSI
- 論理素子 半導体、FET、CMOS、LSI、Mooreの法則
- コンピュータ1 ストアドプログラム方式、メインフレーム
- コンピュータ2 ミニコン、マイクロプログラム方式
- マイクロプロセッサ1 4-64ビットMPUの発達
- マイクロプロセッサ2 命令セットアーキテクチャ、スタックマシン、ハードウェアセキュリティ
- メモリ1 SRAM、DRAM、ランダムアクセス、メモリ階層、不揮発メモリ
- メモリ2 キャッシュメモリ、仮想メモリ、MMU
- 高性能プロセッサ1 命令パイプライン、遅延分岐、分岐予測
- 高性能プロセッサ2 SPECTRE脆弱性、SIMD並列、スレッド並列
- IoTデバイス ARM, mbed, RTOS, デバイスドライバ
- IoTデバイス演習1 センサーとシリアル接続
- IoTデバイス演習2 I2Cインタフェース、Wi-Fiモジュール
- PCと周辺デバイス x86-x64, チップセット、GPU、SSD、UEFI
4.教科書
学生情報サービスおよびGoogle Classroom に掲載する本授業教材PDFを各自で予復習に用いること。オンライン授業については、授業ビデオを受講生の復習用に提供することがある。
5.参考書
- David A. Patterson and John L. Hennessy: Computer Organization & Design: The Hardware/Software Interface (Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design) , Paperback, Morgan Kaufmann、Fifth Edition、2013.
- 成田光影(翻訳)、コンピュータの構成と設計 ハードウエアとソフトウエアのインタフェース 第5版(上)(下)、日経BP社、 2014年
- 阪田 史郎, 高田 広章 (編著)、情報処理学会(編集): 組込みシステム IT Text、オーム社、2006年
- 桑野 雅彦、中森 章 、ARMマイコンCortex-M教科書、CQ出版社、2016.
- 勝純一、mbed電子工作レシピ、翔泳社、2016年
6.関連科目
本科目は、コンピュータ科学の基礎科目であり、特に情報システム構成論、オペレーティングシステム、プログラミング、実践的IoTセキュリティなどの科目の基礎となる。
7.成績評価の方法と基準
各授業の内容について、次回授業のGoogle Classroom上で、5分間の選択式約10問の小テストを課す。その合計点で成績をA, B, C, D に評価する。
8.その他
組み込みデバイス演習環境
●本授業の後半で行う2回の演習では、受講生のWindows PCをWiFiネットワークに接続し、本学が貸し出す開発デバイスをUSBポートに接続して使用する。受講生は、WiFiネットワークとUSBポートを備えたWindows PCを準備すること。事務局で借りることができる。
●演習でのプログラムのコンパイルには、ARM社のmbed を使用する。受講生は、演習授業までにhttps://www.mbed.com/ にアカウント登録し、教員が提供するiisecチームに所属してプログラムを受け取る。方法については、授業の中で説明する。
●感染症の状況に応じて、演習をオンライン・遠隔で実施する場合、弁当箱サイズの演習キットを貸し出すので、自宅等に持ち帰り、各自のPCに接続して使用する。